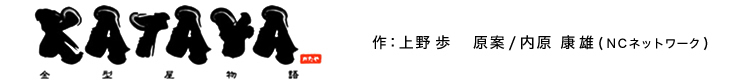
明希子は、静江が本気で言っていたのかと、あらためて驚いた。
「ま……まあ、待てよ」
とベッドの誠一が言った。
「お、おれだって、まだ引退する……つもりは、ない。し、心配するな……て、ての」
「そんなこと言ったって、お父さん――」
静江が不安そうな顔をした。
「だ……だけどよ、なんだ……ほれ……」
誠一がなにか言いたそうにしている。倒れた後遺症で、言葉がすぐに取り出せないのだ。
「“もしも、おれになにかあったときは”でしょ、お父さん」
静江が横から言った。
「うん、うん……そうだけど、さ」
「“あとは頼むよ、アッコ”ね、そうでしょ」
静江がせかすように口を挟む。
それを見ていた明希子は、
「ちょっと、お母さん、お父さんに話す余裕をあげなさいよ」
「そ、そうだよ。……しゃべらせろよ」
「あら、ごめんなさい」
「ま、まあよ、なんかあったときって、も……もう、じゅうぶん、なんかあったんだけどさ」
そう言って誠一が笑った。
「でもよ、う、うちはよ……」
「うちって、会社のこと?」
と静江がきくと、誠一がうなずいた。
「うちはよ、必要とされてる、るんだ。に、日本の産業は……よ、かな、かな、金型産業で……も、も、持ってるんだ。かな、かな、かな、金型産業は日本の……い、い、命だって」
誠一が興奮して言った。
面会時間が終わって、静江と明希子は病院を出た。
「お父さんのまえで、会社のこと話題にしないほうがいいよ」
明希子は言った。
「そうね。あたしも、心配なものだから、つい口にしちゃって」
そう言ったあとで、静江がくすりと笑った。
「右脳型人間、左脳型人間て言葉があるでしょ。お父さんたらね“おれは、そんな
呑気なこと言ってる場合じゃなくなった”って」
明希子も笑って、
「そんな冗談が出るんじゃあ、お父さん、もうだいじょうぶね」
EMIDAS magazine Vol.11 2006 掲載
※ この作品はフィクションであり、登場する人物、機関、団体等は、実在のものとは関係ありません