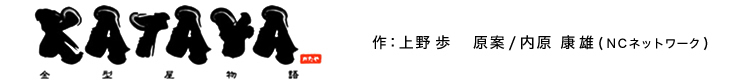
「ダメって?」
「助かったとしても、社会復帰できないんじゃあ……」
「それは最悪の場合よ」
明希子は強い口調で言った。
「最悪の場合は!!……」
静江が大きな声を出して、突然言葉を詰まらせた。そうして、こんどはゆっくりと、
「……最悪の場合は、死んじゃうんでしょ」
「ねえ、お母さん、しっかりして」
「アッコちゃん、そうなったら、会社をあなたが継いで」
「なに言ってるのよ」
「だって……」
静江がくぐもったような声を出した。
「お母さん、すこし眠ったほうがいいよ」
明希子は押入れから仮眠用の布団を出して、敷いた。静江がくずおれるようにそこに横たわった。
明希子は静江にタオルケットをかけてやった。眼を閉じた静江の頬を涙が伝った。明希子はそれをぼんやり眺めていた。
会社というのは、誠一が経営する花丘製作所のことだ。明希子の実家は東京の下町、吾嬬町で金型の受注生産の工場を営んでいる。従業員は三十名ほど。けっして大きな会社ではないが、誠一は、「日本のモノづくりは、金型産業で持っている」というのが口癖で、気概を持って働いていた。
ずいぶん工場に行っていないな、と明希子は思った。大学を卒業すると間もなく、工場の近くにある実家を出て、ひとり暮らしをしていた。小さな工場が密集する吾嬬町は、よくいえば人情に厚い土地柄だったが、若い明希子にしてみれば、生まれ育ったそうしたコミュニティーからいちど離れてみたいという思いがあったのだ。
午前三時になろうとしていた。静江は低く寝息を立てていた。
明希子は壁に寄りかかり、思いをめぐらせた。
――お父さんがこんなことになるなんて……。
――急変したらどうしよう?
――麻痺が残るっていったけど、寝たきりになるのかしら? それとも車椅子? じゃ会社はどうするの? わたしに会社を継げって本気で言ってるの? わたしのほうの仕事はどうなるのよお。
――それよりなにより助かってほしい。
考えれば考えるほど、よくないことばかりが思い浮かぶ。
明希子はいたたまれず、部屋を出てICUの前に立った。夜の病院の廊下はどこまでも静かで、ICUは暗い廊下に向けて光を放っていた。明希子は祈るような気持ちでその光の部屋を見つめていた。
テーブルの電話が鳴ったのは、一睡もできないうちに窓の外が白みはじめたころだった。明希子は反射的に受話器をとった。父の病状が急変したのかもしれない、と思った。
「検査の結果では再出血は見られません。もうだいじょうぶでしょう」
電話の向こうで松尾の声が言った。
静江と明希子は急いでICUに向かった。
「助かるんですね!」
静江が安心したように言った。
「油断はできません。しかし、お二人には、きょうは帰っていただいてけっこうです」
松尾が、意識はないが少しくらいなら会えると言ってくれた。静江と明希子は白衣とマスクをつけ、専用の靴にはきかえて、ICUに入った。
誠一はたくさんのチューブで機械に繋がれていた。明希子には、そんな父が別のひとのように思えた。いつの間にか、とても齢をとっていた。かし、よく見ると、その顔は、静かでおだやかだった。
EMIDAS magazine Vol.11 2006 掲載
※ この作品はフィクションであり、登場する人物、機関、団体等は、実在のものとは関係ありません