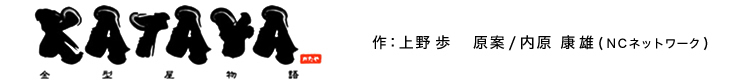
その言葉に父親は、「そうか」と、どうでもいいような素っ気ないこたえ方をした。うれしいが、照れくさかったのだろう。きっと。
当時、藤見は大手電機メーカーに勤めていて、秋田にある工場に配属されていた。夏休みが終わり、勤務先にもどった藤見は、退社の意思を伝えた。
「メーカーではどんな仕事をしていたんですか?」
明希子が藤見にきいた。彼の話に自分の姿を重ねていた。
「経営管理本部という部署に席を置いていました。資金繰り、固定資産管理、原価管理といったあたりが担当です」
「うわぁ、わたしの苦手な分野」
明希子は言った。
藤見が笑って、
「親父は、プラスチック成型加工工場、藤見製作所の二代目でした。祖父が起こした会社でしたが、吾嬬町でも走りのプラスチック屋だったんです」
話をつづけた。
いままで事務職だった藤見が現場の作業をする。それは想像以上に困難なことだった。 たしかに彼はずぶの素人だったが、誰にも負けるわけにはいかなかった。平均年齢が50歳を超えるベテラン揃いの藤見製作所にあって、彼はどの社員よりなにもかもができ、先頭に立って引っ張っていかなければならない。そうでなければ中小企業は成り立たないと思った。従業員は定時で帰し、彼だけは深夜まで働いた。休日にも職場にいた。無我夢中だった。
もうひとつ、藤見製作所の経営体制は旧態依然としたものだった。仕入れ業者との料金交渉は丼勘定だし、受注先への請求書にしてからが手書きのままだった。藤見は、すべてをシステム化することにした。
「――で、どうなったの?」
いま現在、明希子も同様の悩みを抱えていた。
「“やれるものなら、やってみろ!”というのが親父の言い分でした。親父とは、経営方針をめぐってずいぶん言い争いましたよ」
藤見の言葉に、やはりおなじ立場にある入江田が、「ふふん」と笑った。
藤見親子は、ひとつ屋根の下で暮らしながら、3か月も口をきかずに過ごしたこともあったという。どちらも頑固だった。
「大手で学んだことを、すべて中小企業に注ぎ込もうとしていた自分も、すこし走り過ぎていたのかもしれないと、いまにしてみれば思うんですけどね」
藤見製作所の経営は去年の夏ごろから危機的状況になった。
「私が入社した当初から、けっしてよくはなかったんですけど。ついに……という感じでしょうか」
藤見から父親に、「やめないか」と言った。父はけっして首を縦に振ろうとしなかったが、ついには息子の言葉に従った。
藤見は精算人として藤見製作所の廃業をした。
「傍眼には三代目の自分が会社を潰したように映ったでしょうね。しかし、それでいい。あれ以上つづけていたら、さらに多くのひとに迷惑をかけることになったんですから」
藤見がうつむき、
「入江田さん、さっき従業員全員の再就職を私が世話したように言ってましたが、うちは年配の人間が多いでしょ。そうそう受け入れ先もないし、会社を閉めるのといっしょに仕事を辞めた者も多いんです。もっと、働きたかったろうし、生活もあるだろうに……」
聞いていた入江田が深いため息をついて、
「あんた、会社を閉める挨拶にまわってるとき、あちこちからずいぶん冷たいこと言われたそうじゃねえか」
「やめる者に対してはきっとこんなものなんでしょう……“あんたの親父さんの、あんなやり方じゃあ”って、呆れたように言われもしましたけど……」
入江田も明希子も黙っていた。
「でも、アッコさんのお父さんのようにあたたかい言葉をかけてくださる方もいらっしゃったし。吾嬬町ネットワークのみなさんとも会えてよかった。しかし、まあ、私は、ここからも身を引くわけなんですが」
藤見がぐい飲みの酒をひと口なめた。
「親父に言われましたよ、“おまえの人生を狂わせて悪かったな”って。たしかに経営者としては疑問視する部分もあるけど。でも……」
そこで声が裏返った。
「やっぱり……いい親父ですよ。頑固で、職人気質で……私にとっては……なんて言われたって……私にとっては……」
藤見は里芋の煮っころがしでも飲み込むのに苦労しているような表情をしていたが、こらえきれずに泣きはじめた。
吾嬬町ネットワークの面々がこちらを振り返り、しんみりとうなだれた。
入江田がむせび泣いている藤見の背中をさするようにして、
「よくやったよ。あんた、ほんとによくやった」
やさしく繰り返した。
※ この作品はフィクションであり、登場する人物、機関、団体等は、実在のものとは関係ありません