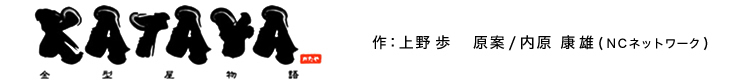

「ごめんください」
明希子が訪ねてゆくと、事務所にいた濃い紺色のウインドブレーカーを着た若い男性が振り返った。
「はい、なんでしょう?」
「花丘製作所の花丘と申します。おはようございます。穂積社長にお会いしたいのですが」
「ああ、社長ですか? 社長なら、きょうは朝練行ってますね」
「アサレン?」
「ええ、コレの」
彼が左手を斜め上に、右手をからだの前に持ってきて、両方の指をうねうねくちゅくちゅと動かした。それが、ギターを演奏する仕種であることが明希子にもわかった。
その時である、
「おはよう! 帰ったど! ははははは!!」
勢いよく事務所のドアが開くと、ギターケースを肩に掛けた中年男性が入ってきた。色黒で、丸顔、からだ全体も丸く、どこかツキノワグマを連想させる。事務所にいた男性が着ているウインドブレーカーとおなじ紺色の作業服姿だった。
「社長、お客さんです」
そう言われて、クマ男がこちらを見た。
「あ、花丘製作所さん?」
「はい」
「入江田専務から聞いてますよ、試し打ちの件でしたね。ほづみ合成工業所の穂積です。協力させてもらいますよ。ははははは!」
サーボモータ駆動の金型は、部品加工から仕上げを経てついに組み上げられた。あとは、三洋自動車で検査という運びになるわけだが、
「そのまえに試し打ちがしたいんです」
明希子は菅沼と藤見に提案した。
「試し打ち……ですか?」
菅沼がいぶかしげにきいてよこした。型の金額を引き上げようという工場長の提案を、当初の見積のままでと明希子は退けていた。請求するべき時には、きちんと請求するから、と。いったいこんどはなにを言いだすつもりなのだろうと思って菅沼もうんざりしているはずだ。けれど、明希子は躊躇することなく、きっぱりとうなずき返した。
金型はあくまで最終製品ではなく、製造用の道具である。成形品の原器となるものだが、明希子の考える金型は、たんにそれだけに留まらない。金型の精度は、成形品精度の一歩上をいくものでなければならないと思っている。なぜなら、一個の金型から大量の精密製品が生み出されるわけだから。
そうして、その最高レベルの技術を要する道具である金型は、一品生産品の典型的な極少量生産品なのだ。まさにモノづくりの粋を集めた芸術品といってもいいだろう。
いったん金型が完成すれば、現場で成形条件を調整することで改良できる程度は限られる。今回のラジエターキャップの型をめぐっては、すでに三洋自動車と笹森産業のあいだで何度もやりとりがあった。そのつど笹森産業は溶接したり、削りなおしたり、部品交換したりを繰り返しているはずだ。
だが、うちは、この金型を一度で通す。難しい型だからこそ、やってみせる。それこそが型屋としての花丘製作所のプライドだ。
「一度で、たってアッコさん、そらあ……」
「三洋自動車が求めているのは仕様書以上に厳しいものです。だからこそ、検査まえに試し打ちをして、最大限の手を尽くしておきたいんです」
以前、グッチー精工でバンパーの試し打ちを見た。グッチーほどの規模と受注力があれば、トライアルのための成形機械を備えることも可能だろう。しかし、花丘製作所には望むべくもない。どこかに協力を仰ぐ必要があった。
明希子は、吾嬬町ネットワークでエコ・トイレットの製作を行った際、成形加工を担当したプラスチック屋に眼をつけた。あそこはいいプラ屋だ。花丘製作所がつくる金型について、捨てる部分のランナーにまで、うちの現場にあれこれ注文をつけてきたらしい。うるさいが、それだけ仕事に対する矜持を感じた。明希子もほづみ合成工業所のまえを何度か通ったことがある。建屋こそ古いが、設備は充実しているようだ。そこで、入江田に紹介してもらうことにしたのだった。
「いやー、地域センターでバンドの朝練しとった。あ、ファクトリー・ファイブっちゅうロックバンド組んどるんよ、おれら」
穂積がいかにもたのしそうに言った。